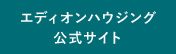第15回 契約不適合責任のうち買主保護の規定について
今回のコラムでは,前回に引き続き,契約不適合責任のうち買主保護の規定について少し詳しく解説していきたいと思います。
契約不適合責任とは
改正民法562条1項では,
「引き渡された目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは」
というように契約不適合責任という概念が採用されました。
これは,目的物が特定物か不特定物かで区別せず,目的物が契約内容に適合していないことに対する責任を認めたものです。この場合の責任として、改正民法は「買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。」と定めています。
従前、目的物に「隠れた瑕疵」があった場合、契約目的が達成できない場合は解除することができ、解除をすることができない場合は損害賠償請求のみをすることができるとされておりました(現行民法第570条、第566条第1項)。
改正の結果,買主保護の手段についても大きく変更されることがわかります。今回は特に,解除ができる場合,損害賠償請求ができる範囲について注意が必要です。
①追完請求
追完請求とは,買主が,売主に対し,売買目的物の修補や,代替物の引渡し,不足分の引渡しを請求することができるという権利をいいます。
現行民法では,例えば,物件の引き渡しを受けたらその物件に雨漏りがあったとしても、上述の通り、契約解除または損害賠償請求しかできないので、買主は売主に対して、雨漏りの原因箇所の修補を請求することはできませんでした。
改正民法では,不動産売買においても買主の追完請求権が認められることになります。さらに付言すると、改正民法では、買主が雨漏りについて知っていた場合でも追完請求ができることになり、注意が必要です。なぜなら,改正民法では,現行民法のように「隠れた」瑕疵であることを必要としていないからです。
そこで,不動産売買契約においては,買主が知っている不適合部分について売主として責任を負わないように,あらかじめ売買契約書において定めておくことが必要になると思われます。
②解除
現行民法では,隠れた瑕疵の存在により買主が契約をした目的を達することができない場合にのみ、契約解除ができました(現行民法第570条、第566条第1項)。
改正民法では,契約不適合の場合に「解除権の行使を妨げない」(改正民法564条)と規定されているので,不動産の買主は相当の期間を定めた催告をしたうえで契約を解除することができます(改正民法541条本文)。もっとも,「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」(改正民法541条但書)は契約の解除ができません。
買主は、契約不適合があっても契約の目的を達成することはできるが,当該契約不適合が軽微とまでも言えない場合には解除ができることになります。
その結果,これまで以上に解除ができるケースが増えると思われます。
軽微といえるか否かは,当該契約及び取引上の社会通念に照らして判断されますが,改正民法のもとでは,軽微な不適合といえるか否かが大きな争点になると思われます。
③損害賠償
現行民法では,瑕疵担保責任は法定の無過失責任と考えられていたことから,瑕疵担保責任に基づく損害賠償の範囲は信頼利益,つまり,瑕疵がないと信頼したことによる利益の賠償に限られていました。
これに対して,改正民法では,瑕疵担保責任を債務不履行の特則と考える契約責任とされたことで、損害賠償の範囲も債務不履行責任に基づく損害賠償の範囲と同じように考えられます(改正民法第564条、第415条)。
すなわち,損害賠償の範囲は履行利益,つまり完全な履行がされたならば得られたであろう利益(たとえば,値上がり利益や転売利益など)も含むことになり,瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求として信頼利益に限定されていた損害の範囲は拡大すると考えられます。
売主としてできること
改正民法のこれらの規定も任意規定であり,特約によって契約不適合責任を限定したり,契約不適合責任を負担しないとすることは可能です。
ただし,宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買については,民法上の瑕疵担保責任のルールを契約書で修正することが原則としてできません(宅建業法40条)。
また,売主が事業者であり買主が消費者の場合には,損害賠償責任を負担しないとする特約は、当該事業者が履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合を除き無効となりますし(民法改正整備法による改正後の消費者契約法8条),契約不適合に基づく消費者の解除権を放棄させる特約は無効とされています(民法改正整備法による改正後の消費者契約法8条の2)。
今回は不動産売買における契約不適合責任のうち買主保護の規定について少し詳しく解説しました。
不動産売買におけるトラブルを予防し,不測の損害が発生することを防ぐためにも,改正民法の内容を踏まえた不動産売買契約書の見直しが必要になりますので注意が必要です。
約1年にわたり,前半は不動産取引に関する一般的な問題点,後半は民法改正に伴う不動産取引への影響について解説させていただきました。
地主さんや家主さん,これから不動産を購入しようと考えている方にとっては,このコラムでは取り扱いがなかった事例や問題点も多々あるかと思います。しかし,問題を抱え込むと解決への道のりは一層遠くなります。いち早く弁護士などの専門家に相談されることが早期解決,より良い解決への第一歩になるかと思います。
最後までお読みいただき,ありがとうございました。
以上
2018年06月15日(金)
第14回 民法改正の影響 ~不動産売買契約における契約不適合責任について~
今回のコラムでは,不動産売買契約における民法改正の影響として,契約不適合責任について解説していきたいと思います。
契約不適合責任とは
物(目的物)に関する担保責任に関して,現行民法では,瑕疵担保責任(民法570条、566条)と数量不足・一部滅失(民法565条)とに分けて規定されていました。
売主の瑕疵担保責任について,目的物に「隠れた瑕疵」があった場合,買主がこれを知らず,かつ,契約の目的を達することができないときに契約の解除ができる,解除ができないときは損害賠償請求ができるとされていました。
不動産のように,この世にひとつしかないもの(特定物)は,売主が買主に引き渡しさえすれば契約は履行されたといえ,債務不履行責任は生じないと考えられます(いわゆる「特定物ドグマ」)。
しかし,目的物に隠れた瑕疵があって,あとから瑕疵が判明したような場合には,代金の決め方や額そのものが変わったかもしれませんし,契約の目的を達することができなかったかもしれません。
そこで売主は、債務不履行責任は負わないとしても,買主の信頼を保護するために故意や過失がなくても瑕疵担保責任を負わなければならないという,法定責任説が採られていました。
ところが,今回の民法改正で,この法定責任説から,担保責任の性格を債務不履行の特則と考える,契約責任説(債務不履行責任説)へ大きくルールが変更されました。
すなわち,改正民法562条1項では,
「引き渡された目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは」というように、契約不適合責任という概念が採用されました。
これは,目的物が特定物か不特定物かで区別せず,目的物が契約内容に適合していないことに対する責任を認めたものです。
このように,法定責任説から契約責任説へ大幅な転換が図られた結果,買主保護の手段についても大きく変更されることになりました。
特定物売買における現行民法の瑕疵担保責任と、改正民法の契約不適合責任とを比較すると、以下の表のとおりになります。
|
|
現行民法 |
改正民法 |
|
法的性質 |
法定責任説 |
契約責任説 |
|
対象 |
隠れた瑕疵 (570条) |
種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの (改正562条1項) |
|
解除 |
契約の目的を達成できない場合に限定される |
相当の期間を定めた催告の上,解除できる ただし,不履行が社会通念に照らして軽微な場合は解除できない (改正564条,改正541条) |
|
損害賠償請求 |
売主に故意・過失がなくても請求できる |
売主の帰責事由が必要 |
|
追完請求 |
請求できない |
請求できる ただし,買主の責めに帰すべき事由があるときは請求できない (改正562条) |
|
代金減額請求 |
請求できない(数量指示売買をのぞく) |
履行追完の催告の上,追完がないときは減額請求できる |
|
期間制限 |
買主が瑕疵の存在を知ってから1年以内(除斥期間、570条、566条3項) |
買主が不適合を知ってから1年以内に不適合の事実を通知する (改正566条) |
不動産売買における契約不適合責任について
①「契約の内容」に適合するか適合しないかの判断は?
現行民法の「隠れた瑕疵」から改正民法の「契約不適合責任」に変更した趣旨は,瑕疵の有無を客観的に判断するのみならず,契約をした動機や目的など契約の趣旨を踏まえて判断しようというものです。なお,民法改正の経過においても「契約の趣旨」という文言が採用されていました(中間試案54頁)。
したがって,契約の内容に適合するかどうかの判断については,これらの契約の目的や動機も含まれるように売買契約書や重要事項説明書に明記しておくことが必要と思われます。
②不動産売買における追完請求の内容は?
現行民法では不動産の売買で契約当時から雨漏りがあったとしても、買主は売主に対して修補請求はできませんでした。
ところが,改正民法で不動産売買においても,買主の追完請求権が認められたので,その分,売主の負担は大きくなったといえます。
そこで,不動産売買契約においては,買主による追完請求権を行使する際の追完方法,追完の範囲についてあらかじめ売買契約書において具体的に定めておくことが必要になると思われます。
③不動産売買における代金減額請求の方法は?
改正民法で,買主は,相当の期間を定めて履行の追完を催告し,その期間内に履行の追完がないときは,不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができることになりました(改正民法563条1項)。
もっとも,代金をいくら減額すべきなのか,具体的方法までは規定されていません。
そのため,代金減額請求をするとき,減額請求をされたとき,適切な減額かどうかが争いになることが予想されます。
したがって,減額の算定方法に争いが生じないように,売買契約書で減額の算定方法や算定基準について明記して多くことが必要と思われます。
今回は不動産売買における契約不適合責任について解説してまいりました。
今回の改正は,これまでの通説であった法定責任説からの大幅な転換を図り,買主保護の手段についても解除,損害賠償以外にも追完請求,代金減額請求など多様化しています。
不動産売買におけるトラブルを予防し,不測の損害が発生することを防ぐためにも,改正民法の内容を踏まえた不動産売買契約書の見直しが必要になりますので注意が必要です。
2018年06月14日(木)
第13回 賃貸物件の修繕,原状回復について
今回のコラムでは,賃貸目的物の修繕、原状回復について解説していきたいと思います。
賃貸人による修繕
賃貸人は,賃借人に賃貸目的物を使用及び収益させる義務を負います(民法601条)。そのため,賃借人の責任がなく,賃貸目的物に雨漏りが生じたり,トイレや風呂などの設備が故障して使えなくなった場合に,賃貸人は賃貸目的物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います(民法606条1項本文)。
それでは,例えば,賃借人の過失(不注意)で窓ガラスを割ってしまったように,賃借人の責任で修繕が必要になった場合にも賃貸人は修繕義務を負うのでしょうか。
現行民法には,この点について規定はありませんでした。そこで,改正民法において,賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要になったときは,賃貸人は修繕義務を負わないと規定されました(改正民法606条1項ただし書き)。
では,賃借人から賃貸目的物の修繕を求められたとき,賃貸人としてはどのように対応すべきでしょうか。
賃借人の責任でなければ,賃貸人は修繕義務を負います。他方で,賃借人の責任であれば賃貸人は修繕義務を負いません。ところが,賃貸人において,賃貸目的物の破損や故障が賃借人の責任によるものかどうか,判断がつきません。
そこで,賃貸人としては,破損や故障の原因について賃借人から十分に説明を受けたうえで修繕義務を負うかどうか判断しなければならないので,注意が必要です。
ところで,賃貸借においては,その期間中に賃貸目的物を修繕しなければならない場合が多く生じます。そのためにかかる費用として,民法は2つの費用を想定しています。ひとつが,賃貸目的物を通常の用法に適する状態において保存するための費用(必要費)で,他方は,賃貸目的物を改良することにより,物の価値を客観的に増加させるための費用(有益費)です。賃貸借契約においては,賃貸人が必要費や有益費を負担しないとの特約が設けられていることがありますが,このような特約は有効でしょうか。
必要費については,電灯が切れたときに交換するような小規模な修繕であれば,賃貸人がその費用を負担しないとする特約は有効と考えられます。もっとも,屋根や柱といった建物の躯体に関わる大規模な修繕については,これらの大規模修繕の費用を賃貸人が負担しないとの特約は無効と考えられます。このような大規模修繕が必要であれば,賃貸人として賃借人に目的物を使用収益させる義務を果たしていないといえるからです。
有益費については,賃貸目的物の使用収益に必ずしも必要な修繕とはいえず,賃借人の判断で支出する費用なので,賃貸人が負担しないとする特約は有効であると判断されやすいです。
賃借人による修繕
賃借人は賃料を払って賃貸目的物を使用及び収益できるだけなので,賃借人は賃貸人に無断で賃貸目的物に物理的な変更を加える修繕はできないのが原則です。
しかし,賃借人が賃貸人に対して修繕を求めたとしても対応してもらえず,賃借人に不都合が生じる場合もあります。
そこで今回の改正民法では,
①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し,または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず,賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき,または
②急迫の事情があるとき
は賃借人は修繕することができるとされました(改正民法607条の2)。
①について,「相当の期間」とは,故障や破損の規模・内容,必要な修繕の範囲・内容,修繕にかかる費用によってケースバイケースですが,3日から1週間くらいと考えるべきでしょう。
②については,例えば,豪雨災害に伴う雨漏り,給水設備の故障による断水などは日常生活に支障を来たすため,ただちに修繕する必要があるので急迫の事情があるといえるでしょう。
原状回復
居住用マンションや事務所など賃貸借契約が終了した場合,賃借人は賃貸目的物を賃貸人に明け渡しますが,このときに賃借人が賃貸借契約に基づき賃貸目的物の引渡しを受けた当初の状態に戻すことを原状回復といいます。
ところが,原状回復の範囲については,カーペットに飲み物をこぼした跡や手入れ不足の結果生じたシミやカビ,壁に張ったポスターの跡,たばこなどのヤニ・臭いなど,どこまで賃借人が原状回復義務を負うのか,民法に明文の規定はありませんでした。
国土交通省住宅局は,トラブルの多い賃貸目的物の退去時における原状回復について,原状回復にかかる契約関係,費用負担等のルールの在り方を明確にして,賃貸借契約の適正化を図るために,原状回復にかかるガイドラインを発行しています。
今回の改正民法でも,賃借人は,賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において,賃貸借が終了したときは,その損傷を原状に復する義務を負う,とされました(改正民法621条本文)。
これまでも判例において,賃借人の原状回復義務の範囲に通常損耗,経年変化による損傷は含まれないと解されてきたことを明文化したものです。
また,賃借人の責任によらずに生じた損傷については,賃借人は原状回復義務を負わないと規定されています(改正民法621条ただし書き)。
このように明文化されたとしても,当該規定は任意規定なので,特約において通常損耗などを賃借人の原状回復義務に含めることは可能です。
もっとも,これまで同様,通常損耗や経年変化による損傷についてどの範囲で原状回復義務を負わせるのか,具体的に範囲を明示しておく必要があります。賃貸人が原状回復義務を負う範囲を具体的に明示していなければ,特約は無効と解されてしまいますので注意が必要です。
今回は不動産賃貸借における目的物の修繕の負担,原状回復に関する改正点について解説してまいりました。
今回の改正で,これまで規定がなかった点や判例の理解が明文化されました。とはいえ,修繕の負担者や原状回復に関する規定については,これまで同様任意規定であるため,特約を定めることが可能です。賃貸人の立場からは,賃貸借契約書において賃借人が修繕義務,原状回復義務を負う範囲を具体的に定めて明示する必要がありますし,賃借人の立場からはこうした義務に関する契約条項を十分に確認の上,納得して契約を締結する必要があります。
2018年02月14日(水)
第12回 賃貸借の存続期間と敷金の規定について
今回のコラムでは,賃貸借の存続期間と敷金の規定について解説していきたいと思います。
賃貸借契約の期間
現行民法では,賃貸借の存続期間は20年を超えることができない,更新期間も更新時から20年を超えることはできないとされています(民法604条)。
とはいえ,借地借家法の適用がある建物の賃貸借契約については,民法604条の規定は建物の賃貸借には適用されず(借地借家法29条2項),賃貸借期間の上限はありません。
また,建物所有を目的とした土地賃貸借契約についても,借地権の存続期間は30年とされ,契約でこれより長い期間を定めることもできます(借地借家法3条)。
改正民法
改正民法では,賃貸借の存続期間は最長で50年間とされました(改正民法604条)。
上記のとおり,借地借家法で賃貸借契約の存続期間について上限を排除しているにもかかわらず,改正民法であえて賃貸借の存続期間を最長で50年間としたのはなぜでしょうか。
最近では土地の有効活用方法の一つとして,太陽光発電のパネルを設置するゴルフ場など、レジャー施設を運営するために土地の賃貸借をすることが考えられます。このようなケースでは,建物の所有を目的としていない賃貸借であるため借地借家法が適用されず,民法の原則とおり、賃貸借の存続期間は20年が上限となります。しかし,太陽光発電パネルのような大規模な設備を設置させるには、20年より長い存続期間が必要となります。
そこで,改正民法ではこのようなニーズに応えるため,賃貸借の存続期間を最長50年間としました。
このように考えると,賃貸借の存続期間の上限を50年とはせずに,撤廃しても良いのではないかと思われます。しかし,賃貸借の存続期間を無制限としてしまうと,いつまでも賃貸借契約の期間が満了しない状態になり、賃貸人にも賃借人にも酷であることから,上限を撤廃せず、永小作権の上限が50年であることにあわせて,賃貸借の存続期間も20年から50年に延ばしたものです。
敷金の定義
これまで敷金の定義については、明文で定められていませんでした。
改正民法では敷金の定義規定が設けられ,敷金とは,「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で,賃借人が賃貸人に交付する金銭」(改正民法622条の2第1項)のことをいうと規定されました。
名目が「保証金」,「預り金」であっても,賃貸借契約で生じる家賃その他の賃借人の賃貸人に対する債務を担保する目的で預けられた金銭は、すべて「敷金」になります。
では,賃料を滞納している賃借人から、預けている敷金を滞納賃料に充当するように請求することはできるでしょうか。
この点については賃貸借契約書において,賃借人からの敷金の滞納賃料への充当はできない旨の条項が含まれているのが一般的でしたが,改正民法では、賃借人から賃貸物件の明渡前に敷金の滞納賃料への充当は請求できない、と明文化されました(622条の2第2項)。
敷金の返還時期
敷金の返還時期についてもこれまで明文の規定はなく,判例上,賃貸借契約が終了し,かつ賃貸物件の明渡が終了したときと解されていました。
改正民法では,敷金の返還時期について、これまでの解釈を明文化するとともに,返還の範囲についても敷金から未払い家賃その他の賃借人の債務を控除した残額と規定されました(改正民法622条の2第1項1号)。
敷引特約の有効性
敷金を返還する際に一定額を控除したうえで返還する旨の,いわゆる敷引特約は有効でしょうか。
この点,敷金の返還時期,返還の範囲に関する改正民法の規定は,強行規定ではなく任意規定と考えられています。つまり,賃貸人と賃借人との合意があれば、改正民法の規定と異なる合意をすることは可能です。
そのため,賃借人である事業者との間で賃貸借契約を締結する際に,敷引特約を設けることは有効と考えられます。
もっとも,消費者である個人との間で居住用建物の賃貸借契約を締結する際に敷引特約を設けることは,特約の内容によっては消費者に一方的に不利な内容を課したとして、消費者契約法によって無効となるおそれがありますので注意が必要です。
不動産賃貸借における賃貸借契約の存続期間,敷金に関する主な改正点について解説してまいりました。
今回の改正はこれまでの理解を明文化した規定が多いのが特徴ですが,借地借家法の適用のない賃貸借契約など土地の有効活用に有利な改正があります。土地を活用した長期事業の展開をお考えの方は、検討されてみるとよいかもしれません。
以上
2018年01月25日(木)
第11回 保証人に関する改正について(平成32年4月1日改正民法 施工予定)
今回のコラムでも,引き続き不動産賃貸借への影響として、保証人に関する改正について解説していきたいと思います。保証人に関する改正は新設される規定も多く,重要な改正点が多いので注意が必要です。
個人が保証人になる場合の保証人保護
平成29年の民法(債権法)改正より前にも,保証人の保護に関する改正が実施されています(平成16年改正)。
保証人が、自身が負担する上限額等に何ら制限もなく主債務者の貸金債務について保証契約した場合,「まさかそんな大きな金額を保証することになるとは予測していなかった」「こんなに長期間保証しなければならないとは思っていなかった」という事態になりかねず,保証人の保護に欠けます。そこで,平成16年の改正では「貸金債務を個人が」保証する場合には,保証契約は書面による必要があり,かつ,保証人が負担する最大限度額を契約で定めることが必要とされ,これらを定めなければ保証契約は無効とされました。
これにより保証人は、保証契約をするにあたり将来負担する最大限の金額について認識したうえで契約することが可能となり、保証人の保護になります。
平成29年の民法(債権法)改正では,貸金債務に限らず,一定の範囲で生じる不特定の債務の個人保証(個人根保証)まで範囲を拡大し、個人保証人を保護することになりました。
不動産賃貸借契約において,個人が賃借人の保証人になることは,将来の未払い家賃や用法遵守義務違反による損害賠償など不特定の債務を保証することになるので、上記の個人根保証に該当します。
そのため賃貸人は、保証契約にあたり、賃借人の保証人が負担する最大限の金額である「極度額」を書面や電磁的記録で定めておかなければ保証契約は無効となります(改正民法465条の2)。
なお,いわゆる保証会社のような法人が借主の保証人になる場合には、極度額の定めは不要です。なぜなら,保証会社は保証人に関する経済状況について情報収集が比較的容易であり、保証人になるかどうかは借主の経済的信用を評価したうえでの経営判断になるからです。
極度額の定め方
では,賃借人の保証人が負担する最大限の金額である極度額は、どのように定める必要があるのでしょうか。
この点について改正民法(債権法)では文言上明らかにされていませんが,具体的に「〇〇円」と定めるべきと解されています。具体的な金額を定めておかなければ,借主の保証人が負担する最大限の金額を予測できないからです。
しかし,貸主の立場からすれば,賃借人の未払い家賃やそれに対する遅延損害金,用法遵守義務違反があった場合の損害賠償など,将来保証人に請求をする可能性のある具体的金額を定めることは容易ではありません。,極度額を少なく見積もってしまうと、保証人から十分に回収できなくなるおそれもあります。
一方、例えば一般的なアパートやマンションの一室の賃貸借契約において賃借人に生じる債務を保証するにあたって極度額を「1億円」と設定するなど、通常想定される債務より著しく高く見積もることはどうでしょうか。
極度額の上限を定めた規定もありませんが,あまりに過大な極度額を定めることは、実質的に極度額を定めていないのと変わりません。
そのため,過大な極度額を設定することは、公序良俗に反して無効とされる可能性がありますので注意が必要です。保証契約が無効となると,貸主は保証人に対して、一切請求できなくなります。
賃貸人にとっては、適切な極度額を定めることが重要となります。
保証範囲の確定
個人根保証において主たる債務の元本が確定するのは、以下の場合とされました(改正民法465条の4)。
①保証人の財産に対して、強制執行などの申立てがされたとき。
信用が破綻したと定型的に認められ、それ以降に発生する債務まで負担させることは酷であることから,元本が確定するとされました。
②保証人が破産手続開始決定を受けたとき
破産手続において保証人の負債を確定する必要がありますし,保証債務の履行が期待できないので元本が確定します。
これに対して,賃借人が破産しても賃料の滞納がない限り賃貸借契約は続きますので、元本が確定することはありません。
③賃借人または保証人が死亡したとき
個人根保証契約は賃借人と保証人との信頼関係に基づくものであり,賃借人の相続人と保証人との間での信頼関係は希薄であることが多いでしょう。そこで,賃借人が死亡した場合には元本が確定されるとされました。
財産状況の説明
事業のために賃貸借契約を締結し,その賃貸借契約に個人保証人を つける場合には、賃借人(保証委託者たる主債務者)は、下記の事項について保証人に対して説明する義務を負うとされました(改正民法465条の10)。
①賃借人の財産及び収支の状況
②主債務以外に負担している債務の有無,額,履行状況
③主債務の担保として提供しているものの内容
賃貸人の立場で注意が必要なのは,賃貸人が、賃借人の保証人に対する説明をしていない、あるいは説明が虚偽であることを知ることができたとき、個人保証人は保証契約を取り消しできるとされた点です(同条2項)。
賃貸人としては,保証契約取消し予防のために,賃借人に対して賃貸借契約書に財産状況の説明内容を明記させ,保証人に確認の上、署名、押印してもらうことが必要です。
履行状況の説明
個人根保証において、保証人が債権者に対して主たる債務の履行状況に関して情報提供を求めた場合、債権者はこれに応じなければなりません(改正民法458条の2)。
この場合、保証人が法人、個人であるかを問いません。これは主債務者が主債務について債務不履行に陥っているにもかかわらず、保証人が当該事情を知らないために、保証債務が拡大することを防ぐことが目的だからです。
賃貸借契約の場合、保証人から賃借人の賃料支払状況について問い合わせがあった場合,賃貸人は賃借人の賃料支払状況及び滞納状況について説明しなければならず、個人情報であることを理由に回答を拒否できません。
賃貸人が当該情報提供義務に違反したとしても、改正民法に罰則は規定されていませんが,家賃滞納の情報を提供しなかったことで保証人の損害が拡大した場合には、損害賠償の問題になる可能性はありますので注意が必要です。
以上、不動産賃貸借における保証契約の場面に関する主な改正点について、解説してまいりました。今回の改正は新たに設けられた規定も多いです。
賃貸人の立場からは、賃貸借契約に個人の保証人をつける場合には、契約書の文言、すなわち極度額の記載の有無、賃借人の財産状況の記載欄が設けられているかなど、改正民法に対応できているかどうか検討が必要です。
賃借人としても、賃貸人から保証をつけることを求められた場合には、保証人に対して財産状況を説明しなければならず、虚偽の説明をした場合には、賃借人、保証人双方から損害賠償を求められかねないので注意が必要です。
また保証人としては、債権者に対して賃貸借契約の履行状況を確認することができ、自らの保証リスクを低減することが可能です。
それぞれの立場で、民法改正により受ける影響が異なりますので、この機会に確認していただく必要があるかと思います。
以上
2018年01月04日(木)
第10回 民法(債権法)改正が不動産取引全般にどのような影響を与えるのか
民法(債権法)改正とは
民法は国民の経済や生活に関する基本法で、1044条もの条文からなる大法典です。
ところが,現在の民法は明治29年,今から約120年前に制定された法律です。戦後,親族相続法については全面的に改正されたものの、債権法の分野はこれまで大きな改正はありませんでした。しかしながら,民法制定以来の社会・経済の変化への対応が求められているとともに、解釈が分かれていた条文の文言についても判例が蓄積されて一般的な理解として浸透した分野も少なくありません。
そこで,これまでの判例や解釈を明文化しつつ,難解な法律用語を避けわかりやすい言葉で制定する民法(債権法)改正法案が通常国会で可決され,平成29年6月2日に公布されました。
改正された民法(債権法)は,公布の日から起算して3年を超えない範囲内である,平成32年(2020年東京オリンピックが開催される年ですね。)4月1日の施行が有力と言われています。このように,公布から施行までに間があるのは,民法(債権法)が国民経済の基本法であり広範囲に影響が及ぶことから,時間をかけて世の中に周知する必要があるためです。
債権法とは
債権とは,人に対してモノの引き渡しを求めたり,金銭の支払いを求めたりする請求権のことです。この債権は契約によって発生するものであり,債権法の改正とは、契約に関するルールの改正です。
不動産取引においても,不動産売買は,買主が目的不動産の引き渡しを求めたり,売主が売買代金の支払いを求めたりする債権を発生させる契約です。また,不動産賃貸借においても,借主が目的不動産の引渡しを求めたり,貸主が賃料を請求したり,借主の保証人をつけたり,不動産所有者が管理を委託したり,様々な債権が発生します。
そのため,今回の民法(債権法)改正は不動産取引に大きな影響を与えることになりますので,3年後に施行されるまでにしっかり改正点について理解しておいていただきたいと思います。
消滅時効期間の改正
民法(債権法)改正により、消滅時効に関する規定が変更されました。
この変更に伴い,不動産賃貸借契約における賃料債権の時効管理について、注意が必要となります。
《改正前》
改正前の民法では,賃料の消滅時効期間は、賃料を請求できるときから5年間とされていました(改正前民法169条)。改正前民法では,請求権の種類によってさまざまな消滅時効期間が設けられていました。例えば,医師の報酬は3年とされているのに対して,弁護士の報酬は2年とされていました。
《改正後》
民法(債権法)改正では,請求権の種類によって消滅時効期間を区別する合理的理由はないとして、契約によって生じた請求権の消滅時効期間を統一しました。
すなわち,①債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間,②債権者が権利を行使することができることを知ろうが知るまいが、客観的に権利行使できるときから10年間の経過をもって時効消滅するとされました(改正民法166条1項)。
一般的には,賃貸人は賃借人に対して賃料を請求することができることは知っているので、①の5年間が消滅時効期間となります。
もっとも,相続人が被相続人から賃貸人としての地位も相続したときに賃借人に賃料の滞納がある場合には、②によって客観的に権利行使できるときから10年の経過によって時効消滅するケースも想定されますので注意が必要です。
時効消滅を食い止めるために
《改正前》
改正前民法では,債権者が「権利の上に眠っていない」ことを示すために,裁判上の請求,支払督促,調停申立て,催告をすることのほかに債務者による債務承認があれば時効の進行を止めることができました。
《改正後》
民法(債権法)改正では,上記以外に新しい制度が創設されました。
すなわち,権利について協議を行う旨の合意が書面でされたときは,民法が定める期間内は時効が完成しないという,協議による時効の完成猶予(改正民法151条)が新設されました。
法定利率について
《改正前》
賃料などの金銭債務の支払が滞ったときに発生する遅延損害金について、これまで法定利率は、年5%で固定されていました(改正前民法404条)。
《改正後》
低金利時代が長引く昨今,年5%の法定利率は高すぎるとの意見から,改正民法では年3%に引き下げられるとともに,3年ごとに法定利率を見直す変動制とする旨の変更がなされます(改正民法404条)。
したがって、賃貸借契約において、遅延損害金の利率を一定にしておくためには、約定によって遅延損害金の利率を定めておくことが必要となります。
以上のように、賃料に関係のある消滅時効期間,法定利率だけでも大幅な改正がありました。
次回は、特に不動産賃貸借契約においては保証人を必要とすることが多いことから、保証人に関する民法(債権法)改正の要点と、これらが不動産取引に与える影響について解説していきたいと思います。
新しい民法(債権法)の施行は3年先とはいえ,いざ施行されれば知らなかったでは済まされません。特に不動産賃貸業を行なわれている方は、契約書の見直しなど今からしっかりと準備することが必要だと思います。
以上
2017年12月18日(月)
第9回 不動産の売買契約および,売買契約書の記載内容に関する注意点について
今回のコラムでは,不動産を売買する際の売買契約における注意点と,売買契約書の記載内容に関する注意点について解説していきたいと思います。
売買契約は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約束して,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約束することによって成立する契約です(民法555条)。簡単に言うと,お金を支払ってモノを引き渡してもらう契約なので,コンビニやデパートなどの買い物も普段は意識することはありませんが,法律的にみると,当然,売買契約にあたります。
このように日常生活にありふれた売買契約ですが,コンビニやスーパーでの買い物でいちいち契約書を作成することはありませんよね。民法555条が規定しているように,モノを渡す,代金を支払うことを口頭で「約束」すればいいので,契約書を作ることは契約成立のための要件とはされていないからです。このような契約を「諾成契約」といいます。
そのため,普段の生活でなかでモノを売ったり買ったりする際には売買契約書を作成することはありません。
ところが,不動産は売買価格も高額になりますし,土地の面積や建物の状況などを売り主,買い主それぞれが確認したうえで合意したことを書面で残しておくことが将来の紛争を予防する手段になります。そこで,不動産売買契約については一般的に契約書が作成されることになります。
不動産売買契約で問題になりやすい,注意すべき点はどのような点でしょうか。
 まず,土地の境界があります。土地を売買する際には,買い主と隣地所有者との間で境界に関する争いが生じることを防ぐために,売り主が境界を明示しておくことが求められます。境界標がきちんと打たれているのであれば問題ありませんが,境界標がなく隣地所有者との暗黙の了解でフェンスなどが設置されているだけですとあとから問題になる可能性が大きいので注意が必要です。
まず,土地の境界があります。土地を売買する際には,買い主と隣地所有者との間で境界に関する争いが生じることを防ぐために,売り主が境界を明示しておくことが求められます。境界標がきちんと打たれているのであれば問題ありませんが,境界標がなく隣地所有者との暗黙の了解でフェンスなどが設置されているだけですとあとから問題になる可能性が大きいので注意が必要です。
つぎに,土地の対象面積について,契約書に記載した面積よりも広かった,狭かった,という問題が生じることがあります。そのため,対象面積を登記簿に記載されている面積としたうえで,実測面積と齟齬があったとしても代金の精算を行わないことについて合意をしておけば,費用のかかる測量をする必要もありませんし,あとから代金の増額,減額という争いも防ぐことができます。
不動産売買契約書で一般の方にはなじみのない用語として「危険負担」というものがあります。
これは,売買契約を締結した後,物件を引き渡すまでの間に,目的不動産の滅失や損傷したときの“危険”つまり“リスク”を売り主,買い主のどちらが負担するかという問題です。
売り主の過失で火事が起きて建物が滅失したときには売り主が“リスクを負う”,つまり買い主に代金を請求できなくなります。反対に,買い主が何らかの事情で故意で建物を滅失させた場合には,買い主が“リスクを負う”,つまり目的不動産が滅失しても買い主は代金を支払わなければならないことになります。
滅失や損傷の原因が売り主にも買い主にもない,第三者による放火や天変地異などの不可抗力による場合はどうなるのでしょうか。
 これを定めたのが「危険負担」の条項になります。現行の民法では,(滅失した)不動産の引渡しを請求できた,つまり,引渡請求権という債権を持つ買い主(債権者)が“危険を負担する”,債権者主義を規定しています(民法534条1項)。
これを定めたのが「危険負担」の条項になります。現行の民法では,(滅失した)不動産の引渡しを請求できた,つまり,引渡請求権という債権を持つ買い主(債権者)が“危険を負担する”,債権者主義を規定しています(民法534条1項)。
しかし,この規定は任意規定で,当事者の合意によってこの規定と異なる内容で契約することも可能です。
そのため,不動産売買契約書を締結する際には不可抗力で目的不動産が滅失,損傷した場合にどちらがそのリスクを負担することになるのか,十分確認しておく必要があります。
 以上のように,不動産の売買は金額も高額になりのちのち争いになることも多いですし,不動産売買契約書には今回ご紹介した用語以外にも一般の方には難解なものが多々あります。そのような条項について,十分理解しないまま契約書に署名押印して,あとから「そんなつもりはなかったのに」とか「そんなこと知らなかった」と言っても後の祭りです。
以上のように,不動産の売買は金額も高額になりのちのち争いになることも多いですし,不動産売買契約書には今回ご紹介した用語以外にも一般の方には難解なものが多々あります。そのような条項について,十分理解しないまま契約書に署名押印して,あとから「そんなつもりはなかったのに」とか「そんなこと知らなかった」と言っても後の祭りです。
不動産売買契約書に署名押印するときにはきちんと理解してからハンコを押すように慎重に対応することが大切ですね。
2017年11月06日(月)
第8回 不動産の売却時等における賃借人立ち退き等にまつわる法律の解説
前回のコラムでは,不動産賃貸借契約にまつわる注意点と民法(債権法)改正による不動産賃貸借への影響についてお話をしました。
前回のコラムでも解説しましたように,賃貸借契約の存続期間の途中で不動産を売却しても、賃借人が対抗要件を備えている場合には、賃貸人としての地位も不動産の譲受人に移転し、それまでの賃貸人は賃貸借契約の当事者ではなくなります(大判大正10年5月30日,改正債権法法案605条の2第1項)。
ここでいう「賃借人が対抗要件を備えている」というのは,不動産賃借権の登記することのほかに,賃借人が目的不動産の引渡しを受けていることも含みます(借地借家法31条)。
したがって,あえて賃借人に立ち退いてもらう必要はありません。
もっとも,不動産の買主が自分で居住することを予定しているときや建物が老朽化していて建て替えや敷地の有効活用をしたいときには,賃借人に立ち退いてもらう必要があります。
それでは、どのような場合に立ち退きが認められるのでしょうか。
 まず,賃貸借契約において,賃借人である居住者に賃料不払いや建物用法遵守義務違反など債務不履行があり、当該債務不履行が賃貸人・賃借人間の信頼関係を破壊する程度であれば、賃貸人は契約を解除して立ち退きを求めることが出来ます。
まず,賃貸借契約において,賃借人である居住者に賃料不払いや建物用法遵守義務違反など債務不履行があり、当該債務不履行が賃貸人・賃借人間の信頼関係を破壊する程度であれば、賃貸人は契約を解除して立ち退きを求めることが出来ます。
これに対して,債務不履行による解除ではなく、期間満了によって契約更新を拒絶することもできます。
しかし,期間の定めのある建物賃貸借契約について,借地借家法では,賃貸人が賃貸借契約を更新しない場合には,入居者に対して契約期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をして,その更新拒絶には「正当事由」が必要であるとされています(借地借家法28条)。
「正当事由」について少し詳しくお話ししますと,㋐賃貸人賃借人双方の建物使用の必要性については,老朽化による建替えの必要性や,入居者が高齢や病気などで引っ越しが困難など継続使用の必要性を比較することになります。この点については,賃貸人側で,入居者の負担が少なく引っ越しができる代替建物を紹介することでスムーズな立ち退きを進めることが考えられます。
㋑借家に関する従前の経過は,当初の契約締結からこれまでの期間の長短,入居者の債務不履行の有無などです。
㋒建物の利用状況は,事業用か非事業用か,実際に居住しているか,などです。
㋓建物の現況は,老朽化の程度,修繕の必要性とその費用などです。構造が木造か、建築基準法に適合しているか、耐震基準を満たしているかどうかも重要なポイントです。
最後に,㋔財産上の給付をする旨の申出というものが,いわゆる立ち退き料にあたります。しかし,立退き料を払えば,入居者に立ち退きを要求できるわけではありません。あくまで最終的に「正当事由」を補う要素にすぎません。
近年の裁判例では,立退料の支払と引換に賃貸借契約解除,建物明渡請求が認められた事例があります(東京地方裁判所平成25年12月11日,事業用建物につき東京地方裁判所平成25年6月14日)。もっとも,いずれの事例も建物が老朽化していたり,早急に耐震補強が必要であったという事情がありましたのでご注意ください。
なお,賃料を滞納して任意の明渡しにも応じない賃借人を契約解除して退去してもらうにはどのような方法が必要でしょうか。
 賃借人が任意の明渡しに応じない場合には,裁判所に建物明渡しと未払い賃料及び明渡しまでの使用料相当の損害金を請求する訴訟を提起します。
賃借人が任意の明渡しに応じない場合には,裁判所に建物明渡しと未払い賃料及び明渡しまでの使用料相当の損害金を請求する訴訟を提起します。
賃料を滞納しているといえども,賃借人の同意を得ずに勝手に鍵をかえて追い出す,居室内の動産を勝手に処分することはできません(自力救済の禁止)。
訴訟において,賃料滞納により当事者間の信頼関係はすでに破壊されていると認められ、賃貸人の請求を認容する判決を出してもらって,ようやく強制執行に取り掛かることができます。
明渡しを命じる判決に基づいて強制執行するには,まず,裁判所に判決が執行力を有することを証明する文(執行文)を付与してもらい,判決が賃借人に送達されたことを証明する送達証明を裁判所から付与してもらい ,強制執行の申立てを裁判所に行います(民事執行法25条、29条)。申立てには、執行官への手数料として予納金(基本金額6万5000円)が必要です。
申立てがあると,執行裁判所は通常,強制執行を実行する日までに任意で建物を明け渡すように明渡し催告を行います(民事執行法168条の2第1項)。
賃借人が明渡し催告にもかかわらず建物を明け渡さない場合は,執行官が立ち合いのもと,専門業者がカギを開錠,家具や荷物を強制的に運びだします。これを「断行」といいます。これらの搬出にかかる費用(一般的に30万円~50万円程度)は,強制執行を申し立てた者が負担します。
以上のように所有する不動産を賃貸すると,簡単に立ち退きを求めることはできませんし,強制執行によって立ち退きを求める場合でも多くの時間と費用を費やすことになります。
不動産を賃貸する場合には、立ち退いてもらうときのことをも考え、活用方法を慎重に検討することが大切ですね。
以上
2017年09月28日(木)
第7回 不動産を賃貸するときにどのような契約ができるのか
前回のコラムでは,中古不動産をリフォームする際の建築基準法などによる規制についてお話をしました。
最近は「不動産投資」に関する書籍がたくさん出版されたり,セミナーや講演が行われたりしているように,親から相続した不動産や購入した中古住宅を賃貸して賃料収入を得ている方も多いように思います。
そこで,今回のコラムでは,不動産を賃貸するときにどのような契約ができるのか,不動産を売却して手放すことも視野に入れた場合にどのような契約がいいのか,について解説していきたいと思います。
また,今年の通常国会で120年ぶりに民法(債権法)が抜本改正されました。改正法が施行されるのは平成32年ごろを予定されていますが,契約のルールを定めた債権法の抜本的な改正によって不動産賃貸借契約にどのような影響が生じるのかについても触れておきたいと思います。
賃貸借契約とは
不動産賃貸借契約は,貸主が目的物となる不動産の使用及び収益を借主にさせること,借主が賃料を支払うことを約束する契約です(601条)。
賃貸借契約については民法に規定されていますが,建物の所有を目的とした土地の賃貸借,建物の賃貸借については借地借家法という特別法においても規定されています。
賃貸借の存続期間
現行民法では賃貸借の存続期間の上限は20年とされています(民法604条)。
もっとも,借地借家法では,借地権については存続期間は30年とされていますし(借地借家法3条),建物の賃貸借については上記の民法604条の規定は適用されないため,20年を超えた存続期間を定めることができます(借地借家法29条)。
この点,改正債権法では賃貸借の存続期間の上限を50年とすることで,賃貸借全般に関して経済活動上の規制を排除しつつ,所有者に過度な負担にならないよう配慮しています。
賃貸借の更新
また、建物の賃貸借契約の更新については借地借家法26条及び同28条に規定されていますが,建物の賃貸人からの更新拒絶,解約申し入れは,いわゆる「正当事由」が必要となります。
賃貸人からの更新拒絶,解約申入れによる賃貸借契約の終了には,借地借家法28条により「正当事由」が必要とされています。
「正当事由」の判断基準として,借地借家法28条は,
・当事者双方が建物を使用する必要性(賃借人が高齢で引っ越し先を見つけることが困難などの事情)
・借家に関する従前の経過(賃料滞納の有無などの事情)
・建物の利用状況(店舗利用か居住目的利用か)
・建物の現況(築年数など老朽化,建替えの必要性の程度)
・財産上の給付をする旨の申し出(いわゆる立退料の有無,金額の多寡)
を考慮するとしています。
このように,借地借家法は賃借人の保護を目的とした規定が多いため,賃貸人としては更新拒絶,解約申し入れをして,自身や家族が不動産を使用しようと思っても解約できないということが想定されます。
定期建物賃貸借契
そこで,建物の賃貸借については,定期借家契約というものがあります(借地借家法38条)。これは,期間の定めのある建物賃貸借で,かつ,契約の更新がなく,公正証書等の書面で契約されるものをいいます。建物のオーナーからすれば,当初から契約していた期間が満了することで確実に契約が終了するので,建替え予定のある建物や,転勤で空き家になっている自宅などの物件も容易に貸すことができることになります。
もっとも,借りる側からすると,契約の更新ができず期間の満了によりおのずと引越ししなければならなくなるデメリットがあるので,一般的には,定期借家契約の場合は,普通建物賃貸借契約よりも低い水準で賃料を設定することが必要となります。
賃貸人たる地位の移転
不動産を賃貸したものの,賃貸借契約の存続期間の途中で不動産を売却すると賃貸借契約はどうなるのでしょうか。
現行民法では明記されていませんが、判例では,賃借人が対抗要件を備えている,すなわち,建物賃貸借において建物の引き渡しを受けている場合で,賃貸人が不動産を売却したときは,賃貸人としての地位も不動産の譲受人に移転し,それまでの賃貸人は賃貸借契約の当事者ではなくなるとされています(大判大正10年5月30日)。
そして,改正債権法では,この判例法理が明文化されています(法案605条の2第1項)。
では,賃貸人が不動産を売却したあとも,従前通り,賃貸人として賃料を得ることはできないのでしょうか。
現行民法においては、賃借人の承諾があれば賃貸人の地位をそのまま留めることで,不動産を売却したあとも賃料収入を得ることができます。
そして,この点について,改正債権法の法案605条の2第2項は,
・賃貸人の地位を留保することの、譲渡人・譲受人間での合意
・譲渡人・譲受人間の賃貸借契約の締結
を要件として賃貸人の地位の留保を認めています。そのため,改正債権法においては賃借人の承諾がなくとも賃貸人の地位をそのまま留めることが可能になると思われ,賃貸人は賃料収入を引き続き得ながら,不動産を売却することが容易になると思われます。
敷金
敷金については、現行民法に定義や敷金返還請求権の発生要件を定めた規定はありませんでした。
そこで,改正債権法では,敷金について,「いかなる名目によるかを問わず,賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で,賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されました(法案622条の2第1項)。
また,敷金返還請求権についても,①賃貸借が終了し,かつ,賃貸目的物を返還したとき,または②賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき,に発生するとされました(法案622条の2第1項)。
その他にも賃貸借関係において債権法改正がなされましたが、契約内容などを吟味せず所有する不動産を安易に賃貸してしまうと、結局自分が使いたいときに使えなかったりしてしまいます。また、賃借人の資力などをよく確認せず賃貸したため賃料が回収できなかったり、物件に汚損破損を加えられたりすれば資産そのものの価値も下落してしまいます。
不動産を賃貸する際には将来のことも見据えて慎重に検討することが大切ですね。
以上
2017年08月17日(木)
第6回 中古不動産をリフォームする際の注意点について
そこで,今回のコラムでは,購入した中古不動産をリフォームする際の注意点について解説していきたいと思います。なお,リノベーションとリフォームという用語は区別して用いられることがありますが,このコラムでは「リフォーム」という言葉に統一しています。
まず,リフォームをする際に注意が必要な法律は「建築基準法」です
建築基準法は,国民の生命・健康・財産を守るために,地震や火災等に対する安全性や建築物の敷地や周囲の環境等に関して必要最低限の基準を定めたものです。
建物の所有者は,建物を建築するときのみならず,リフォームする際にも建築基準法に違反しない状態を保つことが必要です。これに対して,建築後の法改正によって建築基準法の基準を満たさなくなった建物を「既存不適格建築物」といいますが,既存不適格建築物については後述します。
建築基準法以外にも民法,都市計画法や消防法も問題になることがありますが,今回は建築基準法を中心に解説します。
【建築基準法に違反すると】
建築基準法に違反する違反建築物に対して,特定行政庁は,工事の施工の停止を命じる,相当の猶予期限を設けて建築物の除却・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他違反の是正に必要な措置をとることを命ずることができます(建築基準法9条)。
このように,自由に建築物を使用できないという制約があると,住宅の資産としての価値も損なってしまいます。
また,建築基準法に違反する建築物が原因で他人の生命や身体に損害を加えた場合には,土地工作物の所有者として損害賠償責任を負うこともあります(民法717条1項)。実際にも,新築時点で当時の建築基準法の規定を満たしていなかった建物が地震で倒壊し,1階部分に居住していた賃借人が死亡し,遺族の方が建物所有者を相手に損害賠償請求した事案で,所有者の損害賠償責任を認め1億2900万円の賠償を命じた裁判例もあります(神戸地裁平成11年9月20日判決)。
【建築基準法の規制内容】
①接道義務
建築基準法では,建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとされています(建築基準法43条)。この接道義務を満たさない敷地に建つ建物は建て替えや建築確認申請が必要な増築はできないので注意が必要です。
②サンルームやバルコニーを設置する
サンルームやバルコニーを設置すると床面積が変わってきます。
建築基準法では,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合,すなわち,建ぺい率の上限を定めています(建築基準法53条)。
床面積が変わると,この建ぺい率に影響がでてきます。そのため,床面積を増加する工事は,建ぺい率が制限内におさまっているかどうか,注意が必要です。
③間取りを変更する
 中古住宅では築年数によっては現代のライフスタイルに合わなくなっている物件もあるかもしれません。例えば,襖で仕切られている和室をなくしてリビングを大きくとるなどのリフォームが考えられます。
中古住宅では築年数によっては現代のライフスタイルに合わなくなっている物件もあるかもしれません。例えば,襖で仕切られている和室をなくしてリビングを大きくとるなどのリフォームが考えられます。
建築基準法では,住宅の居室には,居室の床面積の7分の1以上の採光の開口面積,居室の床面積の20分の1以上の換気の開口面積が必要になります(建築基準法28条)。
 和室をなくしてリビングを大きくとるリフォームをすることによって,リビングの床面積が大きくなります。その結果,採光や換気の開口面積も大きくとる必要があることになり,既存の窓よりも大きな窓が必要になることもあります。
和室をなくしてリビングを大きくとるリフォームをすることによって,リビングの床面積が大きくなります。その結果,採光や換気の開口面積も大きくとる必要があることになり,既存の窓よりも大きな窓が必要になることもあります。
【既存不適格建築物とは】
建築当時は建築基準法の基準を満たしていたのに,建築後に基準が厳しく改正された結果,建築基準法の基準を満たさなくなった。こんなときに,「違法建築」として是正命令や使用禁止命令をされたら困りますよね。
そこで,建築基準法では,既存の建築物で,建築基準法の改正によって改正後の基準を満たさなくなった建築物を「既存不適格建築物」として,改正後の基準を満たしていないものの,違法建築とはせず法律上は適法な建築物として現状維持が認められるように扱われています。
ただし,既存不適格建築物をリフォームする際には改正後の建築基準法の基準を満たすことが必要です。増築や改築など大規模なリフォームする際には,建築確認申請が必要となります。
このように中古住宅を購入してからリフォームを予定しているときは購入物件について十分に調査・確認をしたうえで,予定しているリフォームができるかどうか事前に検討しておく必要があります。
せっかく購入した不動産なのに,中途半端なリフォームしかできないとなるとがっかりしますよね。購入してから後悔しないためにも十分に確かめておくことが大切ですね。
2017年07月25日(火)